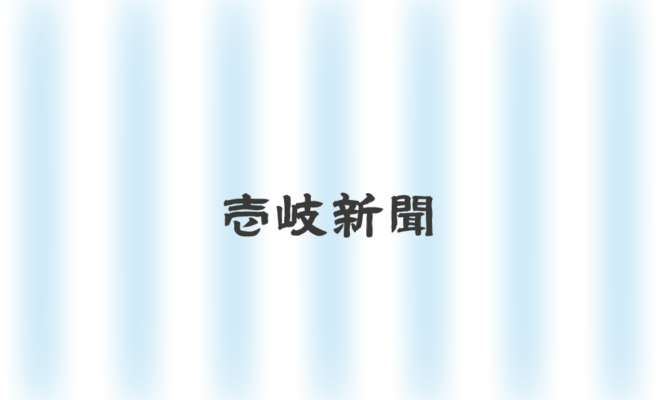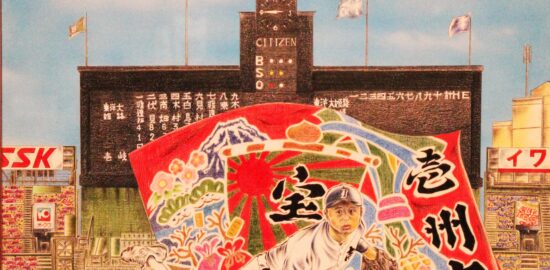芦辺町湯岳興触の久保頭(くぼがしら)古墳から、国内でも珍しい鉄製轡(くつわ)が発見されたことが20日、わかった。同日開かれた一支国博物館の特別講座「壱岐島発掘速報」で、市教委社会教育課の田中聡係長が説明した。田中係長によると、「複環状鏡板付轡C類」に分類されるもので、国内では群馬、京都に次いで3例目と見られ、作り方の特徴は韓国南部の伽耶(かや)地域のものと類似しているという。田中係長は「韓国南部の特徴があり、京都との中間にある壱岐で見つかったことは貴重」としている。詳細は今月中に発掘調査報告書にまとめられる。
久保頭古墳は令和2年度の古墳に登録され、本年度調査が行われてきた。直径14㍍の円墳の可能性が高い。内部は盗掘などによって荒らされ、副葬品の大半は失われたと見られるが、鉄製轡のほか、須恵器、土師器、鉄の刀、鎌、金銅製耳環などが見つかっている。出土品などから6世紀末に築造されて8世紀の初めまで祭祀が行われていたと見られている。
また、田中係長は「南側には9世紀後半から11世紀末に官衛(国府)として利用された興触遺跡があり、久保頭古墳は官衛として機能する以前の興触遺跡を残した集団の有力者が埋葬された可能性が高い」と推察している。
講座ではこのほか、同課の松見裕二係長が郷ノ浦町の車出遺跡について説明。本年度調査した田ノ上の調査区(120平方㍍)から5万8795点の遺物が出土し、そのうち約3万点が赤く塗られた丹塗り土器で、大規模な祭祀が継続的に行われていたことなど説明。また、大量に見つかっている石製のクド石には、表面を削る「斫(はつ)り」が施されており、鉄器を使った加工を行い、石工の技術が進んでいたことを説明した。