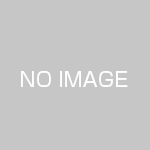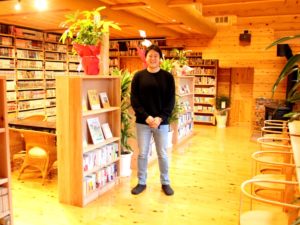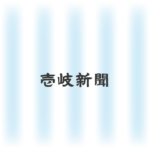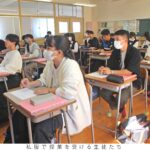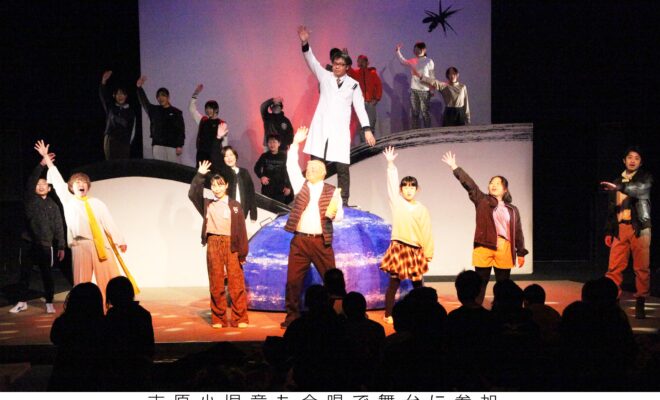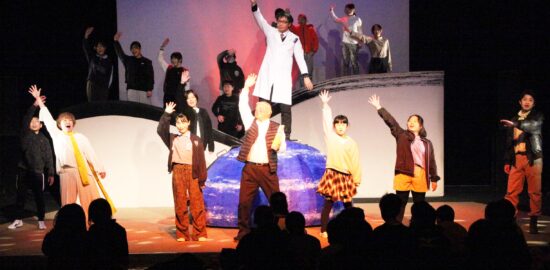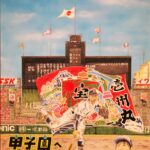市と東京大学先端科学技術研究センター(東京都目黒区、神崎亮平所長)は7日、市役所郷ノ浦庁舎で「壱岐市の持続可能な地域づくりに関する連携協定」の締結式を行った。
市は2015年からの第2次総合計画に「低炭素のしまづくりの推進」を掲げ、再生可能エネルギーの導入促進、低炭素・水素社会の実現へ向けた調査研究に取り組み、18年度には不安定な再生可能エネルギーを水素を活用して安定的に利用して導入拡大を図る「水素・再生可能エネルギー導入ビジョン」を策定。19年9月には国内の自治体で初めて「気候異常事態宣言」をし、50年までにCO2排出量実質ゼロを目指している。
20年度から水素を活用したエネルギーシステムの実証実験に向けた調査研究を行うにあたって、同センターの杉山正和教授に協力を依頼していることから、両社がより連携・協力を深めて持続可能なまちづくりの実現へ向けて取り組むため、連携協定を締結した。
主な連携事項として①再生可能エネルギーの導入拡大・活用②脱炭素・水素社会の実現③持続可能なまちづくり④その他、この連携・協力の目的を達成するために必要な事項、の4点を掲げている。
白川博一市長は「同センターは理工系の先端研究から社会科学やバリアフリーという未来の社会システムに関わる研究まで、多様な研究を推進している。水素活用の実証システムの設計・調査だけでなく、持続可能なまちづくりの総合的な監修も期待しており、この連携協定は大変に心強い。離島地域の活性化策を壱岐から全国へ発信できると確信している」と期待を込めた。
杉山教授は「マネージメントの難しい再エネでは、水素の重要性が高まっている。変換時の発熱ロスを活用するシステムや、量産によるコスト面の問題をクリアしていけば、大いに期待できる。まずはフグ養殖場をフィールドとして実証実験を行う」と話した。
神崎所長は「離島環境の中で地球の未来を考えている壱岐市の取り組みに感銘を受けた。当センターは国内外15自治体と連携協定を結んでいるが、エネルギーに関しては初めてとなる。まずはエネルギーから始めるが、それが地域の魅力・価値になっていけば、人口減少問題の解決や子どもたちの育成など、まちづくりにつながっていく。科学と技術とアートのハーモニーで未来の社会システムを形にしていくことが、当センターの使命だ」と壱岐市のまちづくりに全面的に協力していく意向を示した。
◆水素・再生可能エネルギー導入ビジョン
昨年9月議会でエコアイランド推進事業(約2千万円)として可決された。「Power to Gas」とも呼ばれ、再生可能エネルギー(太陽光、風力など)の導入を促進するため、余剰となる再生可能エネルギーを水素として貯蔵し、必要に応じて再エネルギー化するシステム。20年度は約2億円をかけて実証実験システム設備を導入する予定。
本市は九州本土と海底ケーブルでの系統連系がされておらず、また揚水発電も行っていないため、供給量過剰による大規模停電事故を回避するために、再生可能エネルギーの接続可能量は太陽光5・9MW(メガワット)、風力1・5MWに制限され、すでに制限を越える接続がされているため、冷暖房などの需要が少なく太陽光発電量の多い「春季・好天・日曜」を中心に、出力抑制が頻繁に行われている。この無駄をなくし、CO2排出削減につなげていくため、蓄電池の活用とともに水素貯蔵の研究を行っていく。