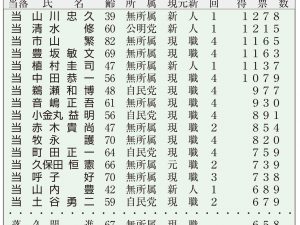弥生時代の環濠集落「カラカミ遺跡」(勝本町)で、国内で初めて鉄生産用の地上炉が複数見つかった。市教育委員会が14日、本年度発掘成果現地説明会を行い、明らかにした。
市教委によると、炉跡は竪穴住居跡内から見つかった弥生時代後期(紀元1~3世紀)のもの。床面に直径約80㌢の範囲で焼けた土が広がっていることから、床面に直接炉を作る「地上式」と確認した。この住居は生活用ではなく、鉄を生産する鍛冶工房だった可能性があるという。これまで国内で確認されている炉は地面に穴を掘った地下式だった。
今回の炉は韓国南部の遺跡などに見られる精錬炉跡に似ており、市教委は「カラカミ遺跡では鉄素材が多く出土していることからも、精錬炉だった可能性がある」と指摘。一帯からは鉄をたたいたり、研いだりしたとみられる石も出土しており、「中国、朝鮮半島で使われなくなった鉄製品などを溶かし、武具や農具に加工して、北部九州などに供給する中継交易拠点だったのではないか」とも推測している。
これまで日本で精錬が始まったのは6世紀後半とされており、従来の説の見直しにつながる可能性もある。
カラカミ遺跡は、九州大が05~08年に調査した際に、今回とは別の4基の鍛冶炉跡を発見しているが、今回の発見でこの4基も地上炉だった可能性が出てきた。
市文化財課の松見裕二学芸員は「カラカミ集落は原の辻の“子分”のように見られていたが、それぞれ交流はしていても、商人の集団だった原の辻とは違う、鉄生産という技術がある別の特徴を持った独立した集団だったことが、今回の調査から想像できる」と話した。
本年度の発掘調査で出土した資料は、来年3月7日から一支国博物館テーマ展示室で「市内遺跡発掘調査速報展」として公開を予定している。


.jpg)
-300x200.jpg)