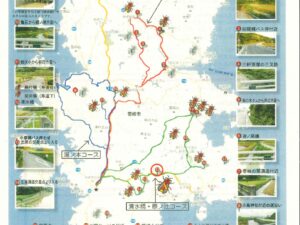一支国博物館の壱岐学講座が4日にあり、同館の河合恭典副館長が国津神社(郷ノ浦町渡良浦)で見つかった「かわらけ」(土師器)について話した。
国津神社は、平安時代にまとめられた延喜式神名帳に記載される式内社(市内に24社)の一つ。今年3月、同博物館主催の歴史探訪ツアーで、河合副館長は同神社を訪れていた。
その際、境内で複数のかわらけを発見していた。中世(平安時代末~戦国時代)後半頃のものと見られ、境内南側の日本庭園で偶然見つけたという。
河合副館長は、かわらけが饗宴や祭りで使われた歴史を、覩城遺跡(芦辺町湯岳本村触)や天水遺跡(石田町山崎触)の例から考察。使われた後は敷地内にまとめて捨てる習慣もあることから、国津神社でも庭園で催された饗宴や祭りで使われた後に破棄されたものとの仮説を立てた。
しかし、壱岐名勝図誌(江戸時代末期)を見ると、同神社に日本庭園が明確に描かれていないことから、中世後期に庭園がない可能性が出てきた。「幕末にこの庭園はなかったということになる。幕末から明治のどこかで造られた可能性がある。(からわけが)宴や祭りの跡ではなかったということになる」と仮説を見直した経過を説明した。その上で「日常的に使われたものでなく、一括で捨てられており、祭祀に関わることで間違いない」とした。
今後、庭園の造営年代や中世に国津神社の年中行事を調べることで、どのようにこの土師器が使われたか明らかにしていくという。