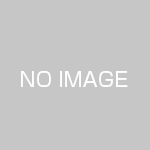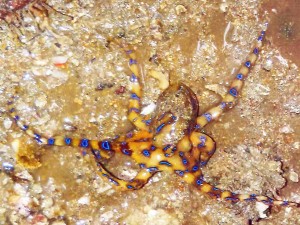歴史論文の全国大会である第14回全国高校生歴史フォーラム(奈良大学主催)の研究レポートの審査結果が9日に発表され、壱岐高校東アジア歴史・中国語コースの歴史学専攻2年生5人の研究論文が優秀賞を受賞した。
応募は全国から114編あり、上位5編が優秀賞、次点5編が佳作に選ばれた。優秀賞の5編は11月14、15日に奈良大学で開催される全国高校生歴史フォーラム発表会で披露され、最優秀の学長賞、次点の知事賞を決定する。新型コロナの影響で同発表会が中止となった場合は、ビデオレターを審査委員が視聴して各賞を決定する。
同校の論文タイトルは「定光寺前遺跡出土の貿易陶磁器からみた中世壱岐の研究」。研究者は吉本大悟さん、竹川柊さん、冨田悠斗さん、益中大輝さん、大島透優さん(いずれも2年)の5人。
5人は11日に一支国博物館で開かれた壱岐学講座「東アジアからみた原の辻遺跡の船着き場遺構」の講演後に、優秀賞受賞を受けて急きょ、研究内容を発表した。
5人は昨年7月から芦辺町の定光寺前遺跡で、2か所の調査区を設置し、古代末から中世の白磁、青磁など中国製輸入陶磁器42点を発掘した。これらの陶磁器の製造年代を分析し、同遺跡近くにあり多くの輸入陶磁器が発掘されている覩城跡の遺物と比較した。
その結果、定光寺前の陶磁器は2期~3b期(11世紀後半~13世紀)が大半で4期(14世紀~15世紀前半)は急激に減少。一方、覩城跡は4期に集中し、5a期(15世紀後半~16世紀前半)から急激に減少していたことから、定光寺前の方が早くから朝鮮と交易があったことが伺えた。
この結果から「覩城跡と定光寺では住んでいた人たちが違い、定光寺前遺跡の周辺こそ、後世に平家に関連すると伝承されるような集団がいた場所ではないか」「1472年に波多泰が亀丘城に居城を築いてから壱岐の中心が郷ノ浦周辺に移り、それとともに深江田原が次第に衰退していったのではないか」「この時期の安国寺の領地の減少(3千石→100石)も深江田原周辺の衰退を表しているのではないか」の3つの仮説を立てた。
「今後はこの仮説を基に、定光寺前遺跡の発掘調査継続、亀丘城の発掘調査、壱岐安国寺の領地についての文献資料調査などで仮説を検証していく」と結んだ。
壱岐高校の生徒は同フォーラムで2017年「馬立(もうたる)海岸遺跡の研究」で優秀賞、18年「大久保遺跡の研究 ~縄文時代晩期貝殻粉混和土器に関する一考察~」で佳作、19年「未解明の古墳時代の集落に迫る~壱岐・車出遺跡とその遺物から見た巨石古墳との関係~」で奈良大学創立50周年記念特別賞を受賞している。