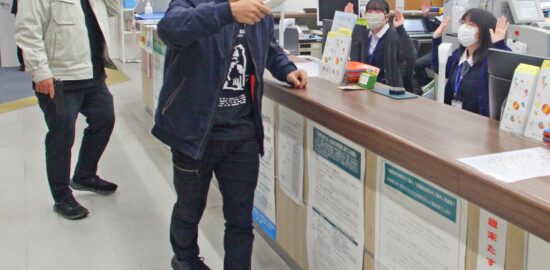「壱岐の自慢1000の宝探し」のワークショップ(NPO法人いき交流文化デザイン研究所主催)が11月20、21、28日の3日間、島内3会場で開かれた。総務省の地域活性化に関する調査研究モデル事業で、名所、自然、グルメ、習慣、伝統文化などから、壱岐に住む人ならではの視点で千個の宝を発掘し、壱岐の活性化に結び付けようという試みだ。
28日芦辺町のワークショップは元九州大学特任教授で博多まちづくりなどに取り組んできた戸島義成さん、和歌山大学産学連携・研究支援センターの吉田潔客員教授、福岡・柳川市で実際に「1000の宝」を発掘して観光に結び付けている「まちづくりディレクター」福田忠昭さんの3人が講師を務め、各地の町づくりの事例などを紹介した。
戸島さんは「町づくりの基本は、まず自分の町を知ることから始まる。町の自慢を探し、それを話すことで人とつながり、観光へのきっかけづくりになる。若者は田舎嗜好が強くなっているという内閣府の調査結果があるし、シニア世代はいままで経験がない形態の旅行に興味を持っている。着地型観光にとってはチャンス」と壱岐の観光客誘致の可能性を指摘した。
吉田さんは「佐賀・唐津市の宝当神社は、その名前に注目してPRしたら、宝くじの高額当選を願う人が年間20万人も訪れるようになった。松浦市の鷹島町も、その名前から“ホークスアイランド”としてソフトバンク・ホークスと連携した。町づくりはこじつけでも成功できる。壱岐にもお宝地蔵があるのだから、利用しない手はない」とアドバイスした。
福田さんは「柳川はウナギと川下りしか有名なものがない町だったが、あるものを組み合わせて物語を作り出すことによって、観光客を呼べる商品になった。魚市場で朝ご飯、川下りでスイーツなど、観光振興の連携によりこれまでとは違う魅力を創作することが重要」などと話した。
講義後に20人の参加者が壱岐の宝探し作業に着手。「ヒト・モノ・ココロ・コト・トコロ」の5分野に分けて、身近な宝を書き出した。参加者からは「左京鼻は、江戸時代に干ばつの危機を、陰陽師の後藤左京が祈祷したが雨が降らず、断崖から身を投げようとした時に雨が降り出したという由来がある」「小島神社は、運良く濡れずに渡れれば、そのカップルはうまくいく」など、地元住民ならでは話が次々に飛び出し、30分間で100以上の宝が発表された。
同研究所では市内の全世帯と小・中学校、高校に壱岐の宝募集の応募用紙1万2千枚を配布し、15日まで市役所など公共施設15か所に設置する応募箱でなど回収。結果をまとめて観光事業に結び付けていく。


.jpg)
-300x259.jpg)
-200x300.jpg)