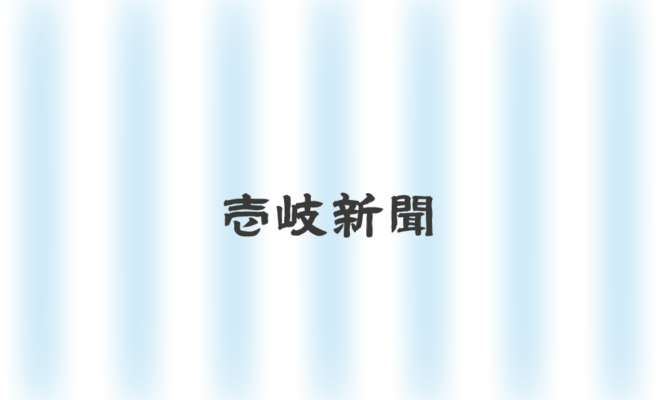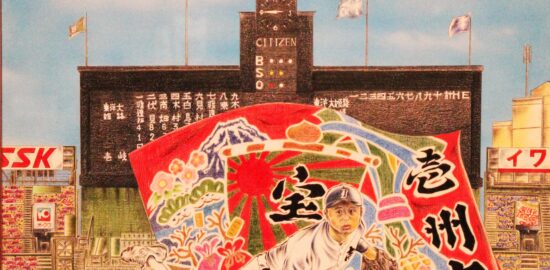厚生労働省がこのほど発表した2018~22年の全国市区町村別合計特殊出生率(1人の女性が生涯に生む子どもの数の推計値)によると、本市は1・80で全国平均、県平均よりは依然として高かったものの、前回の2・14からは0・34ポイントの大幅減少となった。
前々回(2008~12年)は2・14で全国9位、前回は同数値で全国19位の高さを誇っていたが、今回は全国上位50位に入ることができなかった。
県内では佐々町が1・94、平戸市が1・92、五島市が1・88、対馬市が1・87と本市よりも高い数値を示した。全国1、2位が鹿児島県奄美大島の町で、上位20位までの大半を鹿児島、沖縄が占めたように、離島部は全国的に高い数値となっている。婚姻率の高さ、近所や親戚とのつながりの深さ、娯楽環境の少なさなどがその要因として挙げられている。本市もこれまではその傾向を示していたわけだが、急激な数値の下降は「都市化」が進みつつあること、移住者が増加してきたことなどが原因にあるのかもしれない。
6月5日には23年の都道府県別数値が発表され、全国平均は1・20、長崎県は1・49で宮崎県と並んで全国2位。1位は沖縄県の1・60、最下位は東京都の0・99だった。現在の人口を維持していくためには2・0が必要であることを考えると、日本の人口減少が危機的な状況を迎えていることが伺える。
市は婚活、出産・子育て支援の各種施策を展開しているが、日本全国の問題なのだから、これは本来、国の予算で実施すべきことだ。結婚するかどうか、子どもを生むかどうかはあくまでも個人の自由意思であり、多様性を尊重しなければならない。身近である市が「婚活を」「出産を」と声を上げることは、市民により強いプレッシャー感じさせることになりかねない。
市が最優先で取り組むべきことは、人口が減少しても現在と同じ生活環境を維持していくことができるような各種基盤整備を行うことではないだろうか。
社説
人口減少でも生き残れる施策を