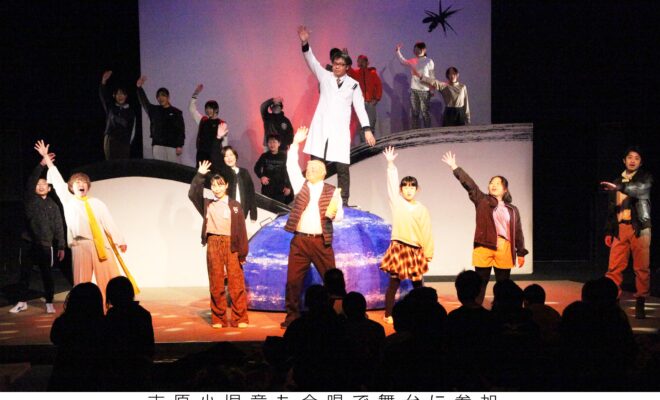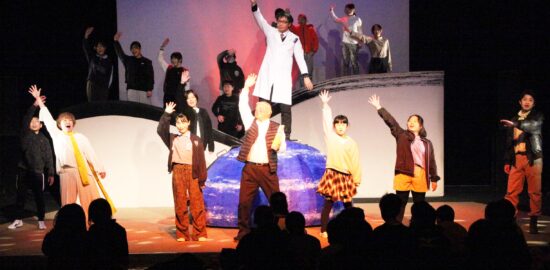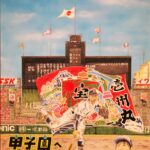文部科学省は19日、公立小中学校の統廃合に関する手引案を公表した。複式学級があったり、クラス替えができない1学年1学級以下となる小中学校に対し、統廃合するかどうかの検討を各自治体に求める一方、存続させると判断とした場合は情報通信技術を活用した授業を行ったり、他校と合同授業を行うなどの対策を促した。
文部科学省は19日、公立小中学校の統廃合に関する手引案を公表した。複式学級があったり、クラス替えができない1学年1学級以下となる小中学校に対し、統廃合するかどうかの検討を各自治体に求める一方、存続させると判断とした場合は情報通信技術を活用した授業を行ったり、他校と合同授業を行うなどの対策を促した。
壱岐市の場合、4月から統廃合される三島小以外は、当面は現在のまま存続されることが決まったが、盈科小以外のすべての小学校がこの基準に含まれる。人口減少・少子化の進行で、近い将来、再び統廃合問題が議題に上がってくるはずだ。
大規模な学校にも善し悪しがある。かなり規模が違うため単純に比較はできないだろうが、私の出身高校は1学年18クラスもあり、しかも毎年クラス替えが行われていた。1クラス50人のため、翌年に同じクラスになるのは平均3人以下。1年間かけてようやくクラスメートと馴染んできたと思ったら、また1からやり直しになる繰り返し。そのため高校時代の同級生で、いまも親しくしている人は皆無である。
クラブ活動も大所帯となり、100人を超える部員がいた野球部では、3年間で練習試合を含めて1試合も出場できない部員も多くいた。教師も各科目に大人数がいたため、2年続けて同じ教師から授業を受けることもなく、「恩師」と呼べるほどの関係を構築することができなかった。
もちろん小規模な学校にも様々な問題はあるだろう。複式学級は、できるなら解消した方が良いかもしれない。学校間に大きな学力、運動能力の差が出てしまうことも避けなければならない。だが小さなクラス、学校はそれだけ団結力が強まり、そこで築かれた関係は一生の財産になるほど濃厚なものになっていくのではないだろうか。
小学校統廃合問題で「小学校は地域のシンボルであり、統廃合には反対だ」というような視点で論じられるが、まずは地域のことよりも、子どもたちにとって何がベストなのかを最重要視して考えて欲しいものだ。
社説
小学校統廃合は児童の気持ち優先で