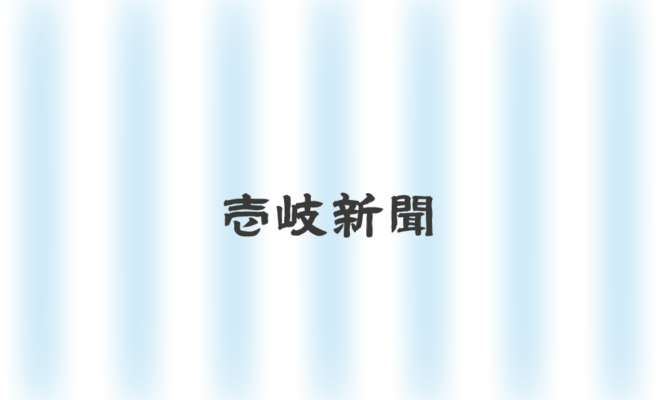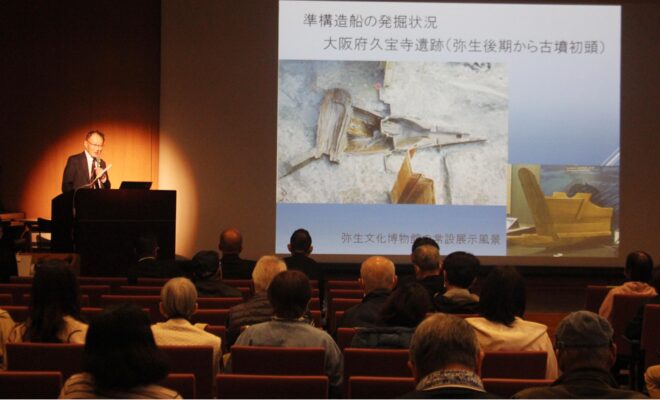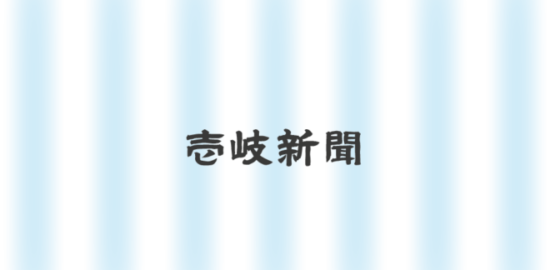マイナンバーカードを健康保険証としても使う「マイナ保険証」でトラブルが相次いでいることについて、岸田文雄首相が陳謝した。新型コロナの接触確認アプリ「COCOA」の時とは違い、システムの不備というよりも、別人情報の紐づけや家族名義の口座登録など人的な入力ミスをした際のセキュリティ対策ができていなかった印象だが、専門家でなくても事前に想定できたことだけに、「お粗末」という言葉がピッタリだろう。トラブルには至っていなくても「マイナポータル」の使いにくさは多くの人が感じており、受注業者だけでなく発注側にも大きな問題があったことは間違いない。
だがそれでも、デジタル化は待ったなしに進めていかなければ、日本は世界から取り残されてしまう。例えば個人が住宅ローンなど金融機関と取引をする際に、所得証明、納税証明、確定申告書、年金支払通知書、印鑑証明、住民票など気が遠くなるほど多くの書類をアナログで準備しなくてはならない。このシステムは百年前から変わっていない。
マイナンバーカードを所有していて、銀行口座やe‐Taxに紐づけされていても、デジタル文書での提出が認められていない。しかも書類をスキャンしてメール送信することも認められていないため、現物を持参するか、郵送するしかない。とんでもなく手間がかかる作業だ。
役所などでは「脱ハンコ」の取組が進んでいるというが、金銭が絡む取引ではいまだに実印、銀行印が必要なケースが大半だ。セキュリティを考えれば顔認証、指紋認証の方がはるかに安全であるはずなのに、いまのところ見直される気配もない。失敗はあってもマイナンバーカードの利便性を高めて、デジタル化社会を構築していく必要があるのだ。
壱岐市ではいまだに、コンビニでの住民票等交付サービスを行っていない。「利用者が少なく経費がかかる」のが大きな理由だが、それでもまずはスタートさせることが、壱岐市のデジタル化の第一歩になるはずだ。
社説
失敗続きでもデジタル化促進を