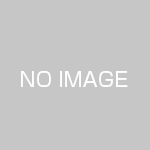先日、本市と日本郵便とのエンゲージメントパートナー締結式が行われた。ごく簡単に説明すると、通常の連携協定を一歩進めた「共創関係」を結ぶことのようだが、市民に詳しく説明するため、この制度について市ホームページに概要が掲載されていた。
その中にこんな説明文があった。「壱岐市でワーケーション(ワーク+イノベーション)を実施することで、社員研修になるとともに、社員の企業へのエンゲージメントも向上」「壱岐市がエンゲージメントパートナーのサードプレイスとなることで、社員のwell‐beingが向上するだけでなく、企業業績の向上にもつながる」。この文章を読んで内容を理解できる市民はどれだけいるだろうか。
カタカナだけではない。日本語でも「鳥の目・虫の目・魚の目・蝙蝠の目の獲得」との説明があった。蝙蝠は「コウモリ」と読む。ビジネスにおいて視野を広げ多面的に見ることを意味するものだが、一般的に使われる「例え」ではなく、正しく理解できない人もいるだろう。
本市の高齢化率は約38%で、3人に1人以上が65歳以上となっている。間もなく仲間入りする記者もそうだが、最近のカタカナ言葉が多用された文章を苦手にしている人は多い。また市政に関わる文章は、中学生でも理解できるものでなければならない。それなのに、特にSDGsに関わる市の説明文は、まるで「判る人だけ判ればいい」とでも言いたげな、独りよがりの難解文が散見される。SDGsこそ中学生にも正しく理解してもらいたいことなのに、その歩み寄りが見られない。
SDGs未来都市・自治体モデル事業に選定されている本市の取組は、目標の2030年のあるべき姿に向けて、大いに意義のある施策が数多くある。だが、その内容が市民だけでなく議員にも正確に伝わっていないため、議会でも批判の矢面に立つことがある。
誰にも分かりやすい言葉で説明することこそが、行政の基本ではないだろうか。
社説
理解を求めるなら平易な言葉で