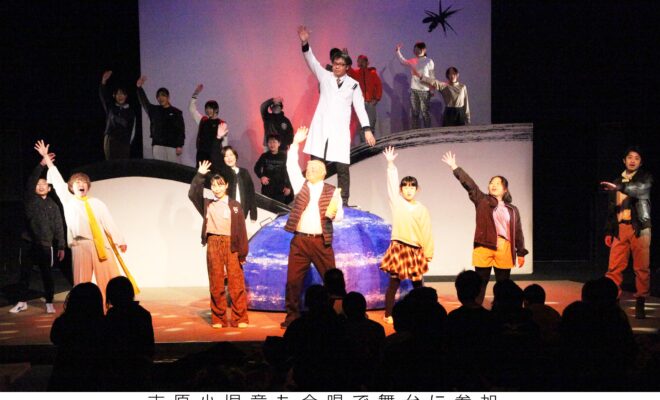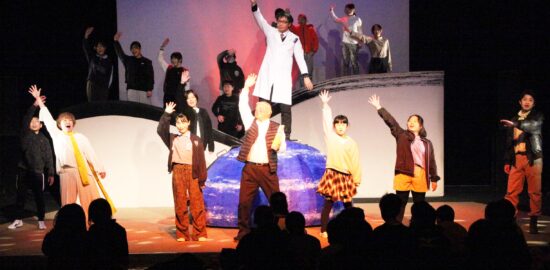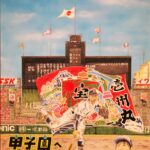3月23日に放送されたNHKスペシャル「里海」は大変に興味深い内容だった。高度経済成長期に赤潮が年間300回近くも頻発し“瀕死の海”と呼ばれていた瀬戸内海の環境が、この数年で劇的に改善されてきた。海岸では“生きる化石”カブトガニが産卵をし、沖ではずっと姿を消していたスナメリが泳ぎ、生態系のピラミッドが確立されつつある。漁業も好調だ。
3月23日に放送されたNHKスペシャル「里海」は大変に興味深い内容だった。高度経済成長期に赤潮が年間300回近くも頻発し“瀕死の海”と呼ばれていた瀬戸内海の環境が、この数年で劇的に改善されてきた。海岸では“生きる化石”カブトガニが産卵をし、沖ではずっと姿を消していたスナメリが泳ぎ、生態系のピラミッドが確立されつつある。漁業も好調だ。
復活の要因とされているのが、かきの養殖筏(いかだ)だった。赤潮の原因であるプランクトンを、かきが捕食することで水の透明度が増す。かき1個で1日に風呂桶1杯分のろ過を行うと言われている。かきの殻には様々な生物が付着し、付近には新たな生態系が生まれる。
水が透明になると太陽光が水中深くまで差し込み、海藻が生える。漁師もアマモの種を蒔いて繁殖を助ける。繁茂したアマモは海のゆりかごで、その中には多くの魚などが棲むようになる。
「海の回復は自然に任せるしかない」というのがこれまでの一般的な考え方だったが、人が手を加えることで豊かさを取り戻すこの「里海」と呼ばれる手法は、いまでは世界からも注目されるようになってきた。米国では同様なかき筏が設置され、インドネシア・ジャワ島ではえび養殖とマングローブ植栽による自国版「里海」を展開させている。
海洋環境の悪化に比べれば、回復のスピードは決して「劇的」ではない。だが漁師たちは「継続は力」と、後世のためにアマモの種まき、せん定作業もコツコツと続けている。
壱岐にも漁場藻場研究所が設置されるなど、海洋環境回復の取り組みは行われ始めており、壱岐版「里海」にも大いに期待したいが、回復が必要なのは海だけではない。
「大らかだった昔に比べると、ずいぶんと荒んでしまった印象がする」と言われている壱州人の心の回復も、また大切なことだ。3年目を迎えた壱岐新聞が「かき筏」となり、「里海」を作り出すことができるような記事を、今後も届け続けていきたい。
社説
壱岐の「里海」を目指して