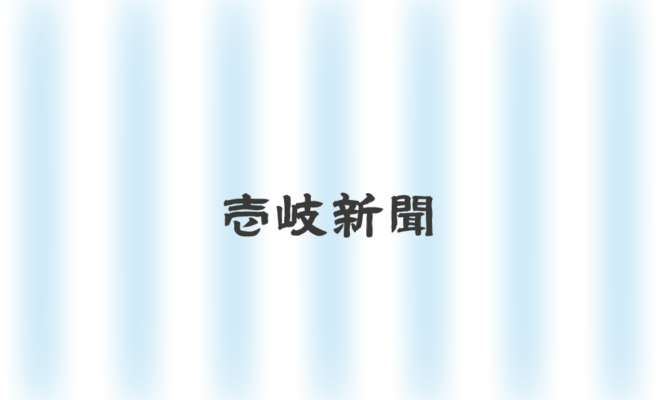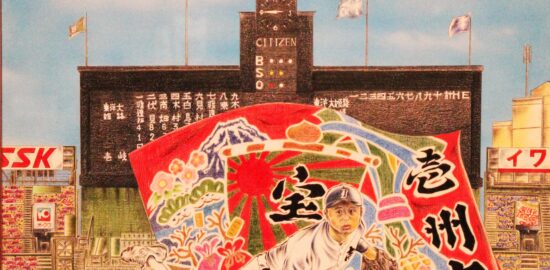5日に辰ノ島で起きた中学生の水難事故は、死者・重傷者はなかったものの、改めて海の安全を考えなければならない出来事だった。
勝本町漁協と十分に協議した上の決断だったとはいえ、遊覧船が欠航する天候・波高なのに辰ノ島で清掃ボランティア活動を行ったこと、監視員は十分にいても7月15日の海開き前に実質的な遊泳を認めたことが正しかったのかなど、命に関わることだけにより慎重な対処が必要だったことは確かだ。だが、遠浅なのが認識されている辰ノ島海水浴場だけに、急激な深みにはまってしまったことは「まさか」の思いが強かっただろう。120人以上もの中学生たちの行動を、完璧に制御、監視することは難しかったようにも思える。
水難事故の完璧な予防策はないが、被害を多少は軽減できる策として、水泳学習の増強が必要ではないだろうか。泳げる人でも溺れることはあるし、泳ぎに自信を持っていることでかえって事故につながるケースもあるが、何かアクシデントがあった場合、泳げればパニックになる度合いが低いことは想像できる。
現在、市内の小学校では年間10単位、中学1・2年は同5単位の水泳授業があり、中学3年は選択制となっている。現在プールが利用できない初山小、芦辺小は、他校や民間施設を活用している。文科省では水泳授業の枠を特に規定はしていないが、他自治体と比べてほぼ同様の単位数だと考えられる。だが、この単位数の水泳授業だけで大半の生徒が泳法の取得まで達成するのはかなり難しいだろう。
本市の場合、離島という環境で、多くの海水浴場がすぐ側にある。「離島の子どもはいつも海で遊んでいるので泳ぎが上手い」というイメージが描かれているが、意外にも泳げない子どもが多い。水泳部が1校もないのも不思議な気がする。
今回のような事故があったからといって、海を危険視するだけでなく、もっと積極的に海に関わり、水泳力を向上させることも必要ではないだろうか。
社説
離島なのに泳げない子どもが多い