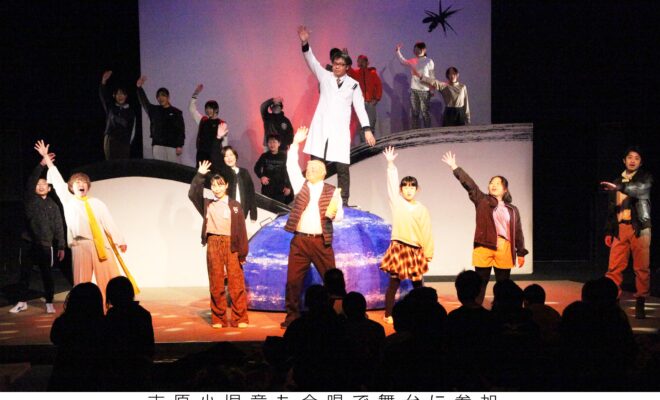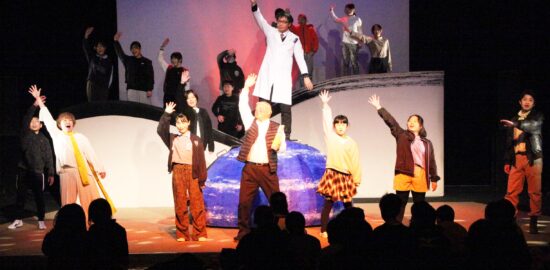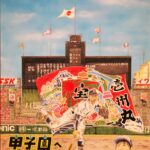先週号でテレワーカーを目指す人たちに、コピー&ペースト(コピペ)での原稿作成が著作権法に違反する恐れがあることを指摘したが、「引用」の条件を満たしていても気を付けなければならないのが「コメント」部分だ。コメントというのは、聞き手によって捉える意味が違ってくることがある。
国際問題にまで発展したアパホテルの客室設置書籍の問題にしても、問題をさらに複雑にしたのは元谷外志雄代表の「中国からの予約ができない」というコメントが、「中国人の予約はできない(受け付けない)」との誤訳で中国の新聞に伝えられてしまったことによる。自分で取材していればこんな間違いは起きにくいはずだが、コメント部分の引用が事態を悪化させてしまった。
そこまで大きな問題でなくても、場を和ませようとしたジョークが、その部分のコメントだけが抜き出されて引用されると、まったく違う意味で伝わってしまうことがある。
例えばお笑い芸人の会見で、ツッコミ役が「しばくぞ!!」とボケ役に“かます”ことがある。取材現場にいれば笑いを取るためのツッコミだと判るが、そのコメントだけが引用されたらとんでもない暴言として扱われてしまいかねない。基本的には、コメント部分は引用するべきではない。
自分で取材した場合であっても、コメントしたことをそのまま正確に文章に起こすと、逆に誤解を招く場合がある。マンツーマンの取材で、記者が取材対象者と親しかったり、取材対象者より若かったりすると、いわゆる「タメ口」で話すことがある。その言葉をそのまま文章にしてしまったら、年配の読者が読むと「なんて言葉遣いの悪いやつだ」と思われる恐れがある。
一方で、決められた文章量の中でなるべく多くの情報を織り込むためには、すべてのコメントを「です・ます調」で書くよりも「だ・である調」にした方が効率的だ。読者が不快にならないギリギリの範囲で語尾を使い分ける技術も、ライターには必要なのだ。
社説
社説・気を付けたいコメントの扱い