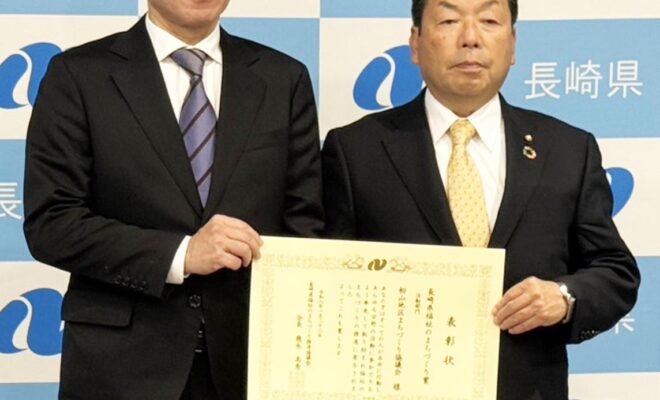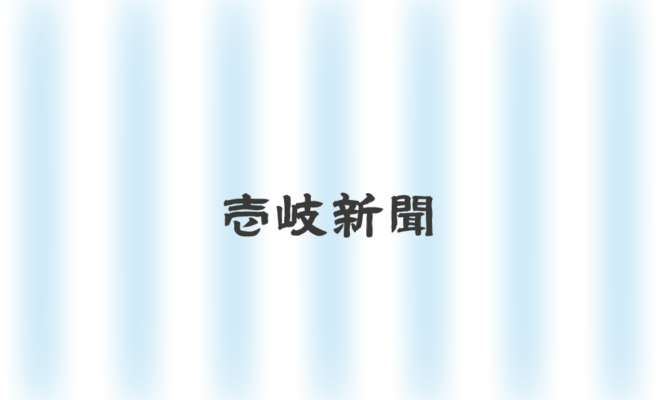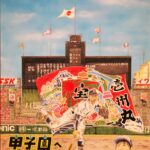8月26日に市議会議場で「子ども議会」が行われた。中学生たちが感じた市政への素朴な疑問に対して、市執行部が回答する恒例行事で、通常の議会とはひと味違う新鮮さ、斬新さを感じさせてくれるイベントだった。
議会を市議会議員と市執行部の「対決」と捉えると、通常の議会では執行部の圧勝と言えるだろう。市が提出した予算案などに対して質問は出るものの、それを覆すことはまずあり得ない。もちろん事前に詳細な打ち合わせなどを行っており、可決される範囲で議案を提出しているという事情もあるし、議員が「市政の常識の範囲」で判断していることもある。
だが中学生たちの質問には、そのような事前の打ち合わせもないし、偏った「常識」もない。思うがままに質問してくる。事前の通告書に記された質問に対しては執行部もそれなりの回答を用意してきたが、石田中が行った再質問に対しては答えに窮していた。また子ども議会後に生徒たちに話を聞くと、「回答には不満が残った」という答えも多かった。純粋な中学生に「大人の理論」はなかなか通じない。
どちらが正しいのかは別にして、このような子ども議会でのやり取りが、本紙のホームページ動画ニュースで、本会議以上に市民に興味がもたれている事実は、議会、執行部とも考え直すべきだろう。
通常の議会を市ケーブルテレビで視聴していても「何を言っているのかまったく判らない」と読者からよく指摘される。だが「子ども議会では『議員』の質問も、執行部の回答も判りやすかった」という。いつもの言語・語尾不明瞭なやり取りではなかったからだ。
新聞原稿は、中学生が理解できるように書くことが基本とされている。来夏からは選挙権が18歳以上に引き下げられる。関係者だけでなく、中学・高校生、一般市民の誰もがすべてを理解できるようなやり取りをしなくては、市議会は興味をもってもらえない。誰のために市議会を開いているのか、聞いている人の立場に立った議会運営が求められている。
社説
社説・子ども議会に学ぶこと