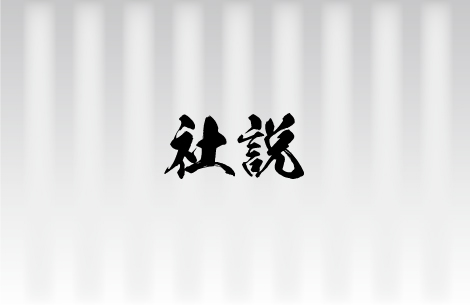神奈川県座間市で起きた悲惨な事件が世間を震撼させている。まだ事件の全貌は明らかになっていないが、1988年の東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件以来、神戸児童連続殺傷、秋葉原無差別殺傷、相模原知的障がい者施設連続殺傷など、社会的弱者をターゲットにした猟奇的な事件が毎年のように起こっている。
先日放映された政治をテーマにしたテレビドラマの中で、小学校が児童に対して「知らない人には挨拶をしないように教えている」との教育方針について、新人市議会議員が「そんなのおかしくないですか」と異議。だが「誰にでも挨拶できるような世の中にしてください」と要望されて、返す言葉を失くしていた。ドラマの中の話ではあるが、それが都会の学校の常識になっている。
突然の雨の中、車で走っていると、びしょ濡れになった小学生が帰路を急いでいる。例えそれが顔見知りの子どもであっても、車に乗せることは絶対にダメ。傘を貸してあげようかと思う気持ちも踏みとどめている。壱岐でも年に1~2回、不審者による声掛け事案が発生している。いまはそういう世の中なのだと納得しなければいけない。
だが壱岐では、中学生、高校生はもちろん、小学生も通学路ですれ違うと、明るい声で挨拶してくれる。信号・横断歩道で停まった車の運転手に対して律儀にお辞儀をする姿は、観光客など来島者を感激させている。素晴らしい文化である。
先日、郷ノ浦町の綿井信久さんが全国防犯協会連合会長表彰を受けた。綿井さんは20年以上にわたって盈科小学校の通学路で、児童の登下校を見守り続けている。綿井さんだけでなく、多くの父母、地域住民、団体がこのような活動を続けているからこそ、子どもたちの「挨拶」の文化が根付いていることを改めて感じた。
安全安心な町づくりは行政だけでは実現できない。市民が一丸となって、子どもたちと気軽に会話ができるような社会を、壱岐では実現させたいものだ。
社説
子どもたちが安心できる町に。